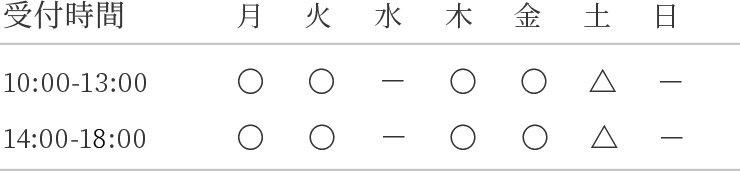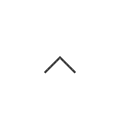- HOME
- 生活習慣改善プログラム
lifecare 虫歯・歯周病は食生活や生活習慣が原因です

調布市国領のフルセン歯科は生活習慣の改善や食育を行う、生活習慣改善プログラムで、あなたの歯の健康をサポートします。虫歯や歯周病になる原因は食生活や生活習慣にあります。当院では、病気の原因に目を向けた予防医療に力を入れています。あなたに合った食生活や生活習慣へ改善するプログラムを実践することが、予防や症状の改善に有効です。
虫歯や歯周病には必ず原因があり、どのような食生活や生活習慣をしているかが大きく影響しています。しかし、ご自身で食生活を大幅に変えることはなかなか難しいものでしょう。だからこそ、口腔ケアのプロによる指導が重要になります。また、タバコを吸う習慣は身体に決してよいものではありません。口腔内の健康だけでなく、身体全体の健康を悪化させます。タバコは身体に百害あって一利なしとお考え下さい。
歯周病を招く生活習慣

「偏った食生活」、「タバコを吸う」、「睡眠不足」、「運動不足」、「ストレスが多い」――。このような生活を送っていると歯周病を招きやすく、症状も進行してしまいがちです。食生活では、精製糖を控え工業製品ではなく、農産物を食べるようにしたいものです。
喫煙は血流が滞り、歯周病を悪化させるため、徐々に本数を減らし、禁煙することをおすすめします。睡眠不足も生活リズムが乱れ、体調を崩しがちになるので、快眠できる環境を整えることが大切です。
また、歯周病はメタボリックシンドロームと大きな関わりがあることがわかっています。適度な運動を行うことが免疫力を高め、歯周病予防に効果的です。心理的ストレスも身体の抵抗力や免疫力を下げるため、ストレスは溜め込まず、解消するように心がけましょう。
食育における大事な3つのポイント
ポイント1:飲み物はお水かお茶! 野菜ジュースもNG

糖分の多いジュースやお砂糖を入れたコーヒーや紅茶だけでなく、実は野菜ジュースも歯の健康のためには控えるのがおすすめです。野菜ジュースは咬まずに野菜の栄養素を手軽に摂取できるイメージのため、次第に咬む習慣が薄れ、きちんとした食習慣が作れなくなるおそれがあるためです。水分を補給する際は、無糖のお茶もしくはお水にしましょう。
ポイント2:まずはしっかりと「咬む食事」

よく咬んで食べることが大切です。当院ではご飯を主食にすることをおすすめしています。小麦粉が原料のパンやパスタを主食にすると、素材や調理法により、油脂分や糖分を多く摂りがちです。また、油分の摂りすぎは肥満のもと、そして糖分の摂りすぎは虫歯の原因になります。そのほか、濃い味付けや柔らかすぎる食材は、よく咬まずに飲み込むことが多く、満腹感を得られずに食べ過ぎることがあるので注意しましょう。
ポイント3:地に足の着いた食生活
現代は洋式の生活に慣れ、テーブルで食事をするご家庭が多くなっています。大人は椅子に腰かけても足が地面につきますが、お子さんは足がぶらぶらと不安定に浮いている状態になります。足をしっかりと地面につけることで、食事のときは顎に力が入り、きちんと咬むことができます。お子さんのためにもしっかり咬める環境を整えてあげましょう。
ちなみに、和式トイレを使っていた昔の人は、しっかり足を踏ん張ることができたので、体幹が鍛えられ更に便秘になりにくかったとされます。
- 足がぶらぶらと不安定


- 足が着地している